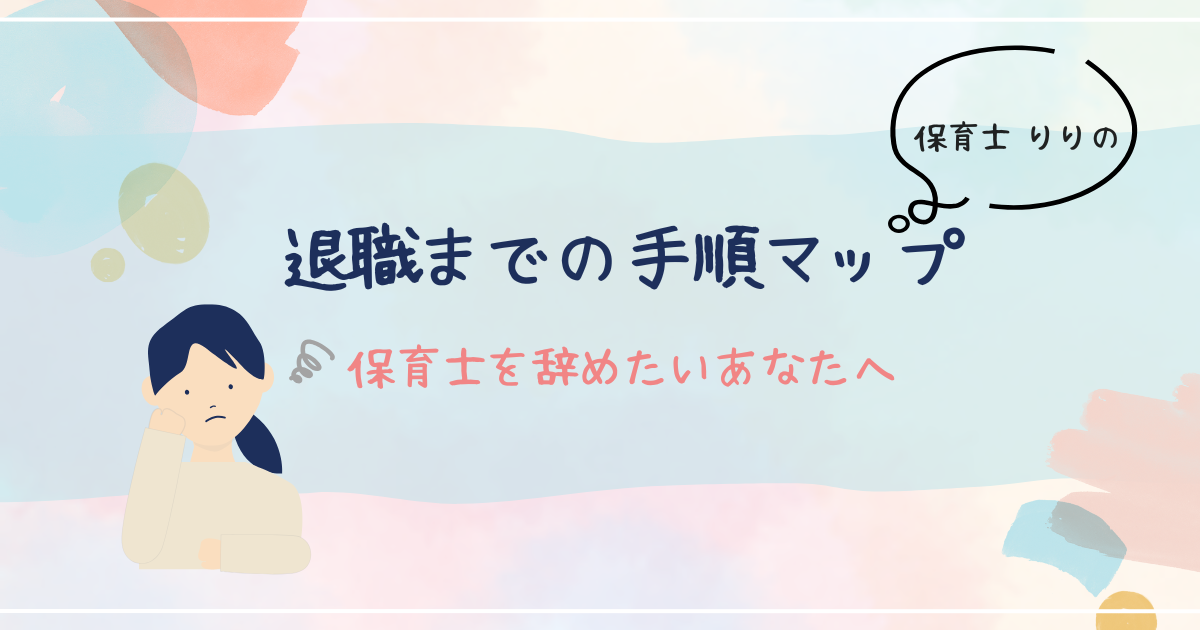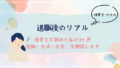保育士をいざ辞める!と決めても、
- どうやって言い出す?
- 引き止められたらどうしよう…
- 手続きって何から始めるの?
と不安になりますよね。
この記事では、私が実際に退職を決意してから退職日を迎えるまでの流れを、リアルにすべてお伝えします。
「辞めたい…」そう思った人が、計画的に退職まで進められるよう参考になれば嬉しいです。
STEP① 園長先生との面談(9月)
私の園では、毎年8月末〜9月に園長先生と一対一の面談があります。
私はそのタイミングで退職を切り出しました。
▷ 私の場合(結婚1年目・子どもなし)
私 「今年度いっぱいで退職しようと思っています」
園長「えっ、もったいない!どうして?」
私 「家と職場が遠くて、子どもができた時に両立できないなと、妊活も考えていて…」
というように、あまり深掘りされにくい個人的な事情を理由に伝えました。
園長先生も「それは仕方ないね」と、すんなり受け入れてくれました。
夫には、県外転勤について行くって嘘ついてもいいよとも言われていました。
他の先生たちの退職理由(実例)
他の先生たちの伝え方も、とても参考になります👇
- A先生(小学生の子ども2人)
→ 家庭との両立が限界。子どものメンタルにも影響が出てきた。 - B先生(独身、婚約・県外転勤理由は嘘)
→ 婚約者の県外転勤に伴う退職(後で少し気まずくなるけど、ばれませんでした) - C先生(独身)
→ 他業種に挑戦したくて退職希望(1番引き止められた)
▶ 引き止められるのが嫌な人は、踏み込まれにくい理由 or 外的要因を理由にすると◎
STEP③ 組合に相談(10月頃)
当時、中堅4人が同時退職予定。
「少しでも残された先生たちの職場環境が良くなれば…」と思い、組合に電話で現状を報告。
結果、転勤希望を出していた職員は全員通りました。
直接的な効果は分かりませんが、声を上げるのは無駄じゃないと実感。
STEP④ 勤務意向調査票の記入(12月)
毎年ある意向調査票に、しっかり「退職希望」と記入。
STEP⑤ 退職届の提出(1月末)
フォーマットに従って提出。
とはいえ、園長先生からは
「今ならまだ取り消せるけど…?」
という引き止めも。ここはブレずに断固たる決意で。
STEP⑥転職活動
公務員は失業手当が出ないため、退職後すぐに収入がなくなります。
そのため、情報収集しながら退職後の働き方を考え、履歴書を書いたり面接に行ったり、
ハローワークに登録に行ったりしていました。
私は自分の好きなことや海外旅行にも行きたいと考えていたので、
正規職員ではなく、パートでとりあえず探していました。
STEP⑦ 退職者向け研修(2月中旬)
期待していた内容と違って、退職金の話だけ。
定年退職者向けの話ばかりでした…
社会保険や扶養の手続きについては何も教えてもらえませんでした。
▶ 自分で調べておくことが大切です!
STEP⑧ 書類の不備チェック・引き継ぎ
退職後に園に来たくなかったので、
- 書類の不備がないかチェック
- 引き継ぎ忘れの確認
- 最後の日に印鑑を園に渡す
など、万全の体制を整えました。
STEP⑨互助組合などに退職届、退職証明願、任意継続組合員申出書を申請する
働いている場所でこのあたりの手続きは変わってくると思いますが
私はこれを退職後に手探りで急いでしたので、
退職前にすればよかったと反省しています。
所属長印がいるものもあるかもしれないので、確認しておいてくださいね!
私の場合は、退職届、退職証明願を郵送で提出して、扶養に入るので任意継続はしませんでした。
独身の先生は転職先もまだ決まっておらず国民健康保険を任意継続する方が安かったので、申出書を出していました。
お住いの役所の国民健康保険の担当者に電話して
給与収入と所得を伝えたら、大体の年間の保険料を教えてくれるので
任意継続した場合と比較して、安くなる方にするのがよさそうです。
退職の反省点とアドバイス
✅ 有給消化の交渉を早めにすべきだった
私は4人同時退職で周囲への配慮から、有給を使う気になれず…。
でも30日以上残してしまって後悔。
本来、有給は「取得する権利」。
労働基準法に基づき、会社側は業務に支障がある場合でも、時期変更のみで拒否は原則できない。
それでも拒否された場合は、まずは人事部に相談。
人事部が対応してくれない場合は、労働基準監督署への相談が有効なようです。
しかし、公務員は労働基準監督署を利用できないため、人事委員会または人事担当部局などに相談。
早めに意思を伝えることで調整の余地はあったかもと悔やんでいます。
✅国民健康保険・年金の手続きを退職前に調べるべきだった
私は退職してから焦って調べ始めました。
結果、夫の扶養に入るための書類を慌てて集めるはめに…。
→ 保険・年金の切り替えは、退職前から要チェック!
→ 夫の勤務先にも早めに相談しておこう!
最後に
退職は、想像以上に体力も精神力も使う一大イベント。
でも、強い意志を持って行動すれば、ちゃんと前に進めます。
そのためにも、
自分の権利(有給など)を放棄せず、
計画的に・戦略的に動いていくことが大切。

あなたの決断、心から応援しています!